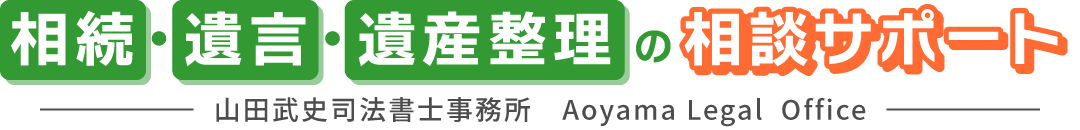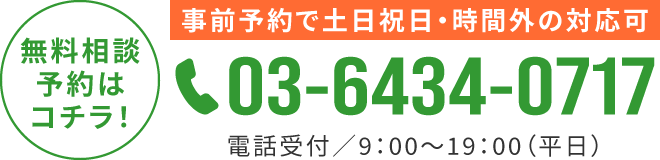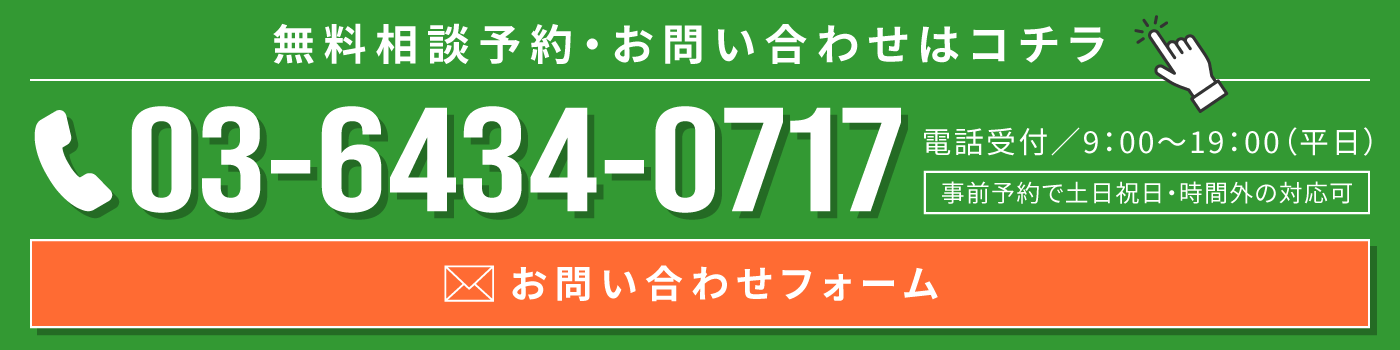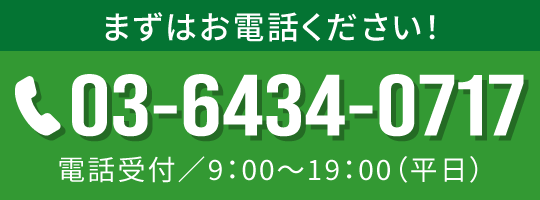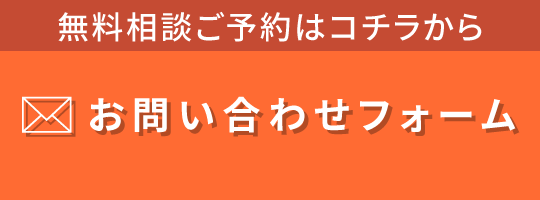記事をご覧いただき、ありがとうございます。司法書士の山田です。
相続が発生したとき、相続人に「未成年者」が含まれるケースは珍しくありません。
例えば、被相続人の子どもがまだ18歳未満である場合や、孫が代襲相続人となった場合です。
しかし、未成年者は法律上、単独で遺産分割協議に参加することができません。
そのため、相続手続きが通常よりも複雑になり、家庭裁判所での手続きが必要になる場合があります。
この記事では、司法書士の立場から、未成年者が相続人となる場合の注意点や解決方法を分かりやすく解説します。
このページの目次
未成年者は遺産分割協議に参加できない
相続人が複数いる場合、相続財産をどのように分けるかは「遺産分割協議」で決めるのが一般的です。
しかし、民法上、未成年者は法律行為を単独で行うことができません。つまり、遺産分割協議に直接参加することができません。
そのため、相続人が未成年者の場合は 親権者が代理人となって協議に参加することになります。
ところが、親権者も相続人であるケースでは「利益相反」の問題が生じます。
例えば、亡くなった夫の相続人が妻と未成年の子である場合、妻が子を代理して遺産分割協議を行うと、親としてより多くの財産を取得したい思惑と子の利益が対立するため、利益相反となり、法律上は代理は認められません。
このようなときは、家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てる必要があります。
特別代理人が選任されると、特別代理人が未成年者を代理して妻と遺産分割協議を行わことになります。
特別代理人とは?
特別代理人とは、親権者と未成年者の利益が対立してしまう場合に、未成年者の権利を守るために家庭裁判所が選任する代理人のことです。
通常、未成年者の法律行為は親権者が代理して行います。
しかし、上述したとおり相続において、親も相続人である場合には「親が自分に有利に協議を進めてしまう可能性」があるため、公平性を保つ必要があります。
そこで、家庭裁判所が選任する第三者の「特別代理人」が、未成年者を代理して遺産分割協議に参加します。特別代理人は、必ずしも弁護士や司法書士といった法律専門職に限られず、親族などでも選任されることがあるのが特徴です。
特別代理人の選任が必要になるケースとは
相続手続きの中で特別代理人の選任が必要になるケースをご紹介します。
- 妻と未成年の子が相続人となった場合に、妻が子を代理して遺産分割協議を行うとき
- 複数の未成年者が相続人となっており、その法定代理人がまとめて遺産分割協議を行うとき
- 相続人である母(または父)が、未成年の子についてのみ相続放棄の申述をするとき
- 同じ親権に服する複数の未成年者の子のうち、一部の未成年者の子だけ相続放棄の申述をするとき
このような場合は、家庭裁判所に特別代理人選任の申立てが必要となります。
特別代理人選任の手続きの流れ
- 未成年者の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 親権者の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 特別代理人候補者の住民票又は戸籍附票
- 遺産分割協議書(案)や相続財産の資料
- 申立先は未成年者の住所を管轄する家庭裁判所です。
- 申立人は、親権者・利害関係人
- 申立費用 収入印紙800円※申立ての際に家庭裁判所に納める費用です。
上記が特別代理人を選任し、相続手続きを開始するまでの流れになります。
相続登記を含めた相続手続きには、家庭裁判所の選任審判書が必要になるため、特別代理人の選任が必要なケースでは、必ず必要になる手続きになります。
司法書士に依頼するメリット
未成年者が相続人に含まれる場合、通常の相続手続きと比べて、少しお時間やお手間をいただく場合がございます。
司法書士に依頼することで、次のようなメリットがあります。
- 戸籍収集や相続人調査を一括で依頼できる
- 特別代理人選任申立書作成サポート
- 遺産分割協議書の作成から相続手続き完了までを一括して代行
「手続きが難しくて進まない」「書類を自分で準備するのは大変」「家庭裁判所への申立ては不安」という方でも、司法書士のサポートがあれば安心です。
まとめ
未成年者が相続人に含まれる場合、遺産分割協議をそのまま行うことはできません。
家庭裁判所に特別代理人を選任してもらう必要があり、この手続きを経ないと相続手続きが無効になる可能性があります。
必要書類の収集や裁判所への申立てには時間がかかるため、早めの準備が大切です。
当事務所では、相続手続きに関する初回相談を承っております。
「相続人に未成年者がいる」「特別代理人の選任が必要か分からない」とお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
▶ 無料相談はこちらから 問い合わせフォーム