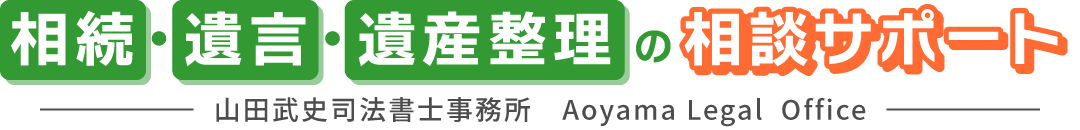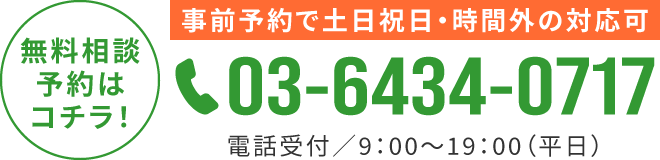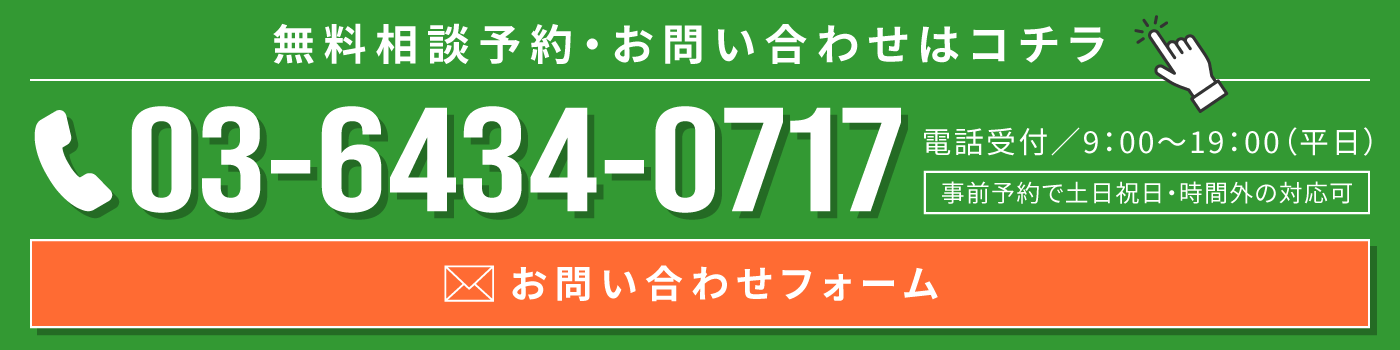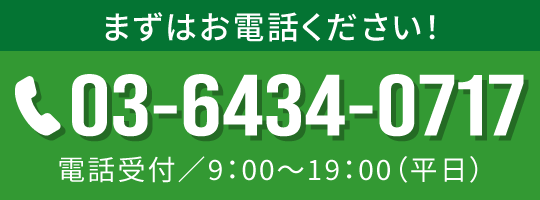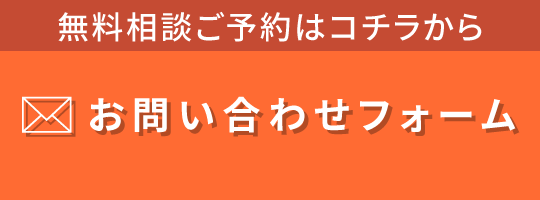記事をご覧いただき、ありがとうございます。司法書士の山田です。
「親が高齢になり、一人で暮らすのは心配だから施設に入居してもらいたい」
「でも、その費用をまかなうために実家を売りたい」
そんな時に大きな壁となるのが、親が認知症を発症すると不動産の売却ができなくなる という現実です。
「まさか…」と思われる方も多いですが、これは法律上のルールです。
この記事では、なぜ売却できなくなるのか、そしてどんな事前対策があるのか司法書士の立場から解説します。
このページの目次
認知症になると不動産が売れない理由
不動産の売買契約を成立させるには、売主である不動産の所有者本人の意思確認 が不可欠です。
たとえば、実家が親の名義であれば、売却契約書に署名・捺印するのは親本人です。
しかし、所有者である親が認知症を発症すると、
- 契約の意味を理解できない
- 不動産を売る理由や金額について判断できない
といった状態になることが少なくありません。
この場合、「本人の意思に基づく契約」とはいえず、この状況のまま契約したとしても契約自体が無効になる可能性があります。そのため、不動産業者や司法書士、銀行も取引に応じません。
つまり、実家が売却できず、事実上“凍結”されてしまうことになります。
成年後見制度を使う場合の注意点
「それなら成年後見制度を使えばいいのでは?」と思われる方も多いでしょう。
確かに、認知症を発症した後に不動産を売却するためには、家庭裁判所に成年後見人を選任してもらう必要があります。
後見人に選ばれた人(家族や弁護士、司法書士などの専門職)が本人に代わって売却契約を行うことは可能です。
ただし、いくつか注意点があります。
- 親が居住している家を売却するには家庭裁判所の許可が必要になる
- 売却代金の使い道も「本人の生活のため」に限定される
- 相続税対策や資産の有効活用といった目的には使えない
- 後見人は毎年、家庭裁判所に収支報告を行う義務がある
つまり、成年後見制度は「本人の財産を守る制度」であり、自由度が高いわけではありません。
成年後見制度は、「成年後見について」もご覧ください。
家族信託(民事信託)という選択肢
そこで数年前から活用されているのが、「家族信託」です。
これは、親が元気なうちに「自分の財産管理を子に託す」という契約を結ぶ仕組みのことです。
信託契約を結んでおけば、将来、親が認知症を発症したとしても、子どもが代わりに実家を管理したり、売却することができます。
成年後見制度と比べると、以下のメリットがあります。
- 柔軟な財産管理ができる
- 相続税対策や資産運用にも活用できる
- 裁判所の関与がなく、家族・親族内で財産管理を完結できる
ただし、家族信託を利用する場合は、信託契約書の内容を慎重に検討して作成しないとトラブルのもとになりますので、司法書士など専門家のサポートを受けることが重要です。
家族信託(民事信託)は、「家族信託(家族のための信託)とは」もご覧ください。
空き家を防ぐために、家族で話し合おう
実家の不動産は「とりあえずそのまま」にされがちですが、親が認知症になると売却できなくなり、結果として空き家化してしまうケースが少なくありません。
空き家は固定資産税の負担や管理の手間がかかるだけでなく、将来的に相続トラブルの原因にもなります。
そうならないためには、
- 実家を将来どうするか(売却するのか、誰かが住むのか)
- 親の施設入居や介護費用はどう確保するのか
- 事前にどう対策するのか
を親が元気なうちに家族で話し合っておくことが大切です。
早めの対策が将来の安心につながる
親が認知症になった後では、不動産を売却するハードルが高くなります。
成年後見制度を使って売却することも可能ですが、制約が多く、資産活用の幅は限られます。
一方で、家族信託などを含めた事前対策を親が元気なうちに準備しておけば、将来の選択肢がぐっと広がり、家族の負担も軽くなります。
大切なのは、「まだ大丈夫」と思える今のうちに動き出すことです。
司法書士は、成年後見や家族信託を含めて具体的な対策をご提案し、ご家族に合った形での財産管理・承継をサポートできます。
実家の将来について不安を感じている方は、ぜひ司法書士にご相談ください。
当事務所からのご案内
「実家をどうするか、家族で話し合った方がいいのかな…」
「でも、何から始めればいいのか分からない」
そんなお気持ちのときこそ、当事務所にご相談ください。
当事務所でサポートできること
- 認知症に備える制度のご案内・提案・実行サポート
(家族信託・任意後見など) - 生前の準備のサポート
(遺言・家族信託など) - 相続や不動産に関するご相談
「相談したら必ず依頼しなければいけない」ことはありません。
ご相談いただくことで少しでも安心していただければと思っています。
どうぞお気軽にご連絡ください。
お電話でのご予約はこちら ⇒TEL03-6434-0717
メールでのお問い合わせはこちら ⇒ [お問い合わせフォーム]